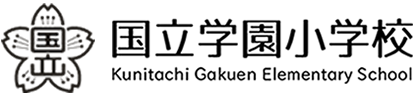学習指導
学びの主体は子どもたち。
見守る教育を推進しています。
子どもたちは21世紀の担い手です。
これからの子どもたちに必要なのは、未知の事態に遭遇したとき、
どう対処したらいいかを「自ら考え、自ら学び」そして、「自ら行動する」力です。
私たちは「学ぶ量を増やす」ことよりも
「自分で学びとろうとする力を育てていく」ことが
大切だと考え、実践を展開しています。

「共に学び合う」授業を目指して…

「学ぶ」ことは一人でもできますが、私たちは「共に学び合う」ことを授業の中で大切にしています。
社会に出たときに、良いアイディアを思いついたとしても、それが相手に伝わらなければ、形になっていきません。学習場面でも同じです。本校の授業は、自分が分かれば自分ができれば、それで終わりではありません。
算数の授業で、分からない子がいたら、どのように説明すれば相手が分かるようになるか、音楽の授業で、リコーダーが苦手な子がいたら、どのように教えてあげれば吹けるようになるか、体育の授業で、縄跳びが上手く跳べない子がいたら、どのようなアドバイスをすれば跳べるようになるか、子どもたちは考えます。
「それは、先生の仕事では?」と思われるかもしれませんが、教師主体ではなく、子どもたち同士が関わり合い、子どもが主体となるような授業のしかけを教師が意図的に作っているのです。
『伝え方を考えて、行動に移してみる。』でも、一回では上手くいかないこともあります。そうしたら、『また違う助言を考えて伝える。』その繰り返しの結果、「できるようになった。」と、一緒に喜び合っている子どもたち。人の成功を自分の喜びとして受け止められる我が子の姿、素敵だと思いませんか。
こうした活動は、本校で大切にしている異学年交流の場にも当てはまります。どうしたら、下級生に上手く伝えられるか、喜んでもらえるか、上級生は考えます。
これも「自ら考え、自ら学び、自ら行動する子ども」の姿です。
学校には色々な子がいますが、『相手の良いところ、苦手なところも含め、お互いを認め合える関係作り』というものが、社会に出たときも大切だと考えます。
私たちは、この6年間で、一人ひとりがそれぞれの輝ける場を見つけ、「12歳の選択」をして巣立っていけるよう全力でサポートします。
教頭 吉村 智美